今日の東京新聞デジタルに,裁判所が速記官を養成しようとしないことに対して問題を提起する記事が載っていた。
最高裁が法廷速記官の養成を1998年に止めてから25年間が経ち,速記官の数は1997年の852人から2022年10月の148人まで減っている。
最高裁は,養成を再開することは考えていないという。
現在では,尋問調書の作成は,録音反訳をメインにしている。
録音し,その反訳書を作成するのである。
しかし,記事にもあるが,証人や供述者の声が小さかったり,もっと難しいのは滑舌が大変悪い場合,録音反訳だと,反訳できない危険が高い。
これに対して,速記では,速記官がその場で,供述者の顔(特に口元)を見ながら,何を言っているのか探りながら速記録を作成できる。
実際に,先日行った尋問では,供述者が高齢で,口の筋肉が弱っているのか,入れ歯が合っていないのか,両方あるいは他の要因もあるのか,聞いていても何を言っているのか理解が難しかった。
が,速記官は,実にキレイに速記録を作った。
録音反訳の方が費用がかからないのかもしれないが,少なくとも一定数の速記官は確保するべきなのではないか?
と感じた。


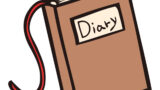

コメント